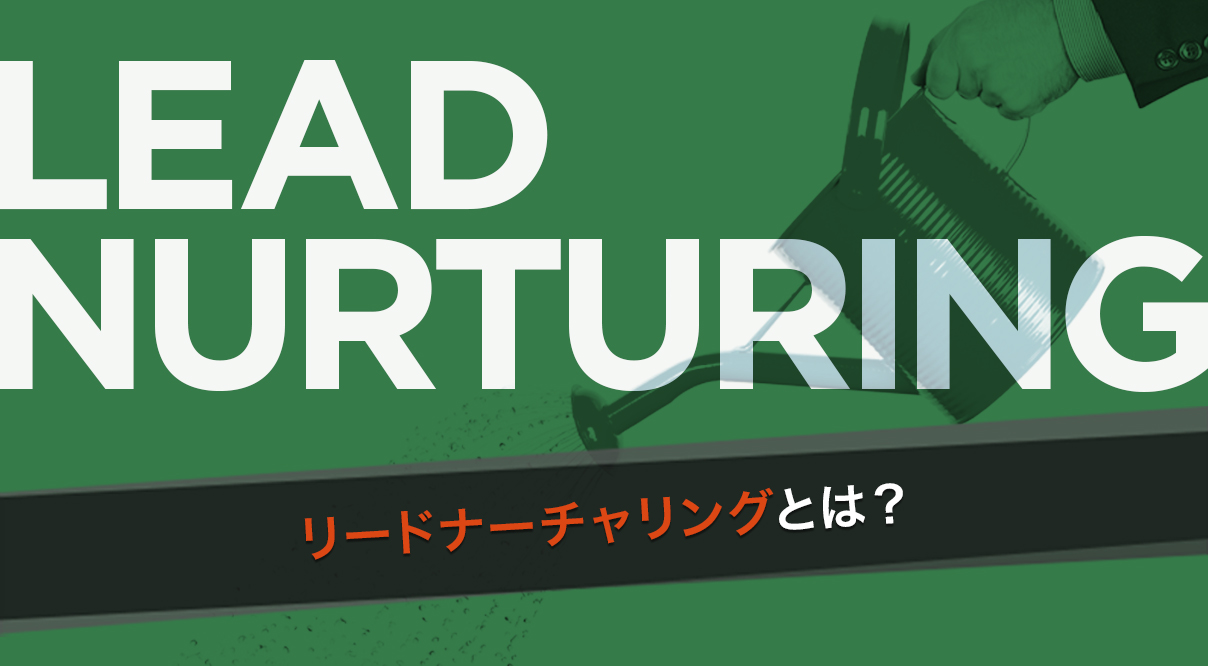テレコールでのリードナーチャリング!展示会後のテレコールを効果的に行うには?
展示会後のテレコールで、アポイントは獲得できるのか?
テレコールと聞くと、【営業=アポ取り】とイメージされるように、多くのBtoB企業では、展示会で集めた数千という名刺をマーケティング部でリスト化し、展示会後にアポイント獲得のためのテレコールを実施しています。
製品・サービスの検討段階で有効なアポ取りのテレコールだが、展示会後のテレコールでアポイントは獲得できているでしょうか?
以前、掲載したこちらの記事
展示会のブース出展を成功させるための4つの検討事項とその準備で説明したように、昨今の展示会の来場者の目的の多くは「情報収集」「市場動向調査」です。
つまり、展示会後も見込み客は引き続き、情報収集中の状態であり、商談を希望する見込み客は非常に少ないと言えます。
展示会後のテレコールは、まず見込み客を絞り込んで実施することが重要となってくるのです。
見込み客側から見ても、アポイント獲得を目的としたテレコールは、ベネフィット(価値)は感じられず、これでは苗段階の見込み客を刈り取っている状態です。
では、見込み客にとってベネフィット(価値)が発生するテレコールとはどんなものがあるでしょうか。
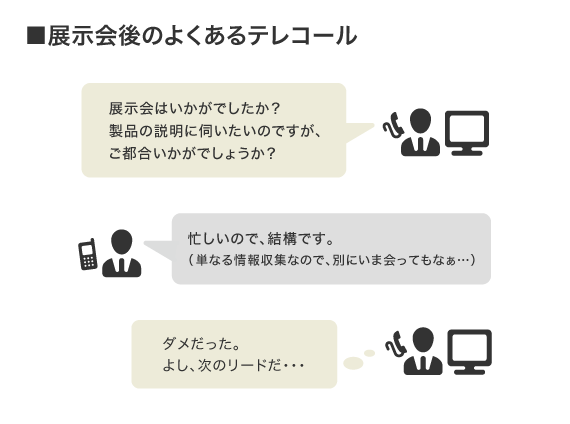
テレコールでも「見込み客の価値を考え、提供する」ことが重要
リードナーチャリングは、見込み客と継続的な接点を持ち、関係性を構築することで、購買意欲を醸成し、成約に繋がる可能性の高い顧客に育成するマーケティング活動です。
そこで、展示会後のテレコールを実施する前に、まずは集めた見込み客の関心・興味を確認し、それぞれの見込み客に対してベネフィット(価値)があるコンテンツ(セミナーやホワイトペーパーなど)を用意しましょう。
そして、テレコールで、見込み客と直接接点を持ち、用意したコンテンツをあてることで、見込み客のニーズを把握していきます。
日本のBtoB企業は、元からオフラインでのコミュニケーションに強く、テレコールは見込み客の声や会話の間合いで、細かいニュアンスを計ることができます。
これはメルマガの配信やWEBのアクセス履歴などのオンラインの施策では、取得できない情報です。
このようにして、ベネフィット(価値)があるコンテンツをテレコールで与え続けることにより、継続的に接点を持ち、見込み客を顧客へと育てていくのです。
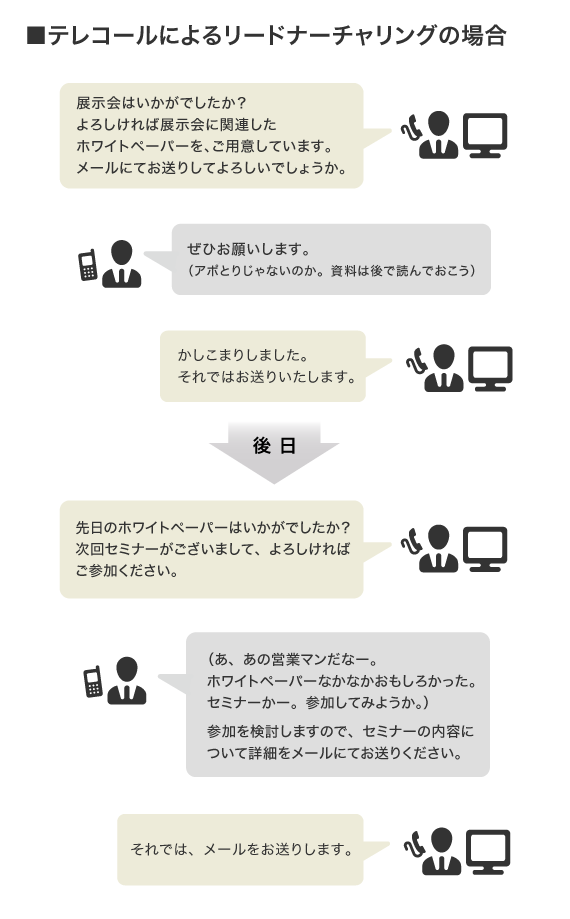
最近では、このテレコールのチームを営業ではなくマーケティングの部門内に置くことが増えていると聞きます。つまり、テレコールというマーケティング活動を通じ、見込み客を育成し、顧客化・案件化のタイミングで営業にパスする仕組みを各社が目指していると言えるでしょう。
見込み客のニーズを把握することで商談をスムーズに
また、展示会後に、メルマガで見込み客と接点を持ち、リードナーチャリングを実施する企業が多い傾向にあります。しかし、ワンマーケティングでは、メルマガでは見込み客と十分なコミュニケーションとることができず、見込み客に事案が発生したタイミングを逃す可能性が高いのではないかと考えています。
実際、弊社ではリードナーチャリング施策の一つとしてテレコールを活用し関係性を深めることで、その後、営業案件として引き合いをいただくことが増えてきています。
通常、新規の顧客への初めての営業訪問と言えば、まずサービスについて、基本的な説明が必要です。更に訪問する時点では、見込み客の関心のポイントがわからないことが多いです。
しかし、リードナーチャリングを経て、営業の訪問に至った見込み客はあらかじめ、セミナーやホワイトペーパーなどのコンテンツを確認しており、ニーズや課題は顕在化していると考えられます。つまり、基本的な説明が不要なので、お客様の課題や疑問の掘り下げにより多くの時間を使うことができるのです。
このようにリードナーチャリングを経た見込み客へ、営業が見込客の抱える課題や疑問に即した説明ができれば、商談に結びつく確率は高くなるのではないでしょうか。
まとめ
BtoB企業の購入のように、費用が大きくなればなるほど、購入決定までのタイミングにオフラインでの接点は必ず発生します。
このオフラインの接点を有効活用することが、見込み客を「顧客化する」重要なポイントです。
展示会後のテレコールをアポ獲得に終わらせるのではなく、ぜひ、見込み客のナーチャリング活動として有効的に活用していただきたいと思います。
Download
Service Plan
ワンマーケティングは、「案件創出」「売上の向上」という成功へ向かって、
ひとつながりのマーケティングフローを構築。
マーケティング戦略設計からMA導入・運用、セールス支援、コンテンツ制作まで統合的に支援しています。
サービスの詳細はこちらから