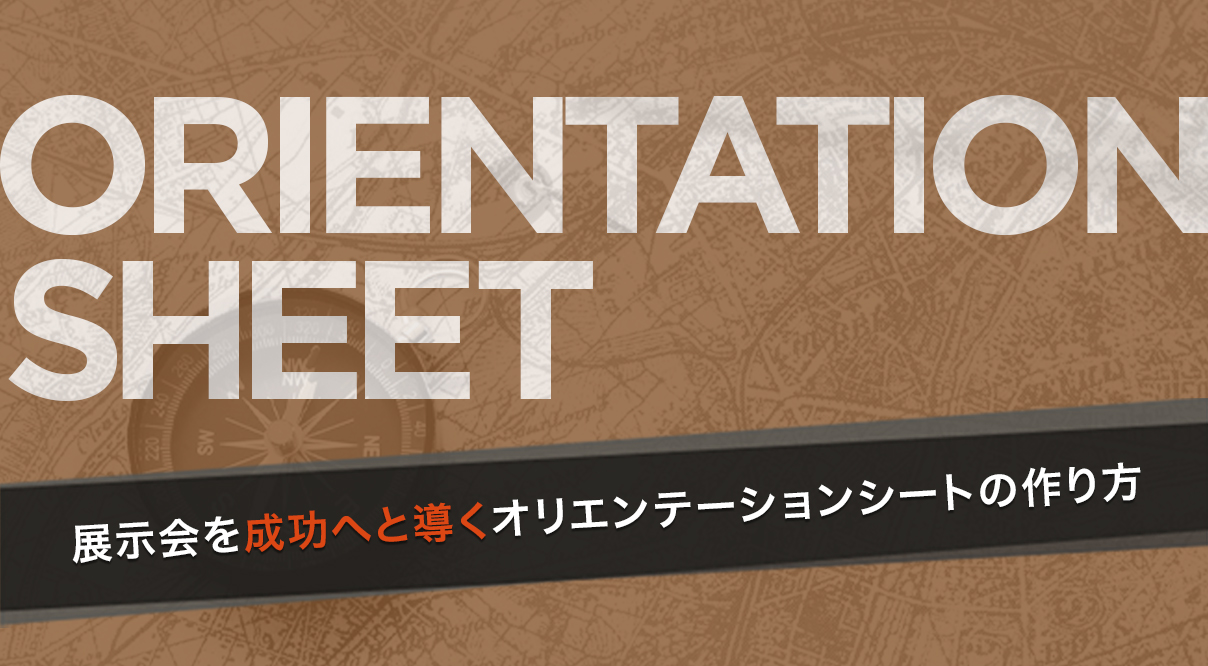真の有効回答を導き出す方法! 展示会のアンケート設計における重要な3つのポイント
アンケート実施の目的とは?
展示会において、アンケートは必須です。実際に展示会を出展している企業なら、アンケートを作成した経験はあることでしょう。しかしながら、アンケートの目的を考えずに何となく作成して、配布していることはないでしょうか?
そもそも展示会の目的は、名刺の獲得(リードジェネレーション)です。そこにアンケートを加えることで、名刺を精査し(リードクオリフィケーション)、来場者に対する今後のアプローチをすすめる上での判断基準にするためにあります。
ここで、問題となるのが、リードクオリフィケーションの技術。つまり、アンケートの設計方法です。何をすれば、名刺を精査することができるのか?担当者の皆さんが、一番頭を悩ますところです。
そこで今回は、アンケートの設計方法を今一度、考えてみましょう。
来場者の時間は限られている
では、実際のアンケートを応える側になって考えてみましょう。
私は仕事柄、展示会のアンケートを見る機会も多いが、そんな中で感じるのは、今一つアンケートの設計が、考えられていないものが多いということです。
特によく見かけるのが、①やたらと項目が多いアンケート、②これを聞いてどうするの?という内容、③長い記入欄があるアンケートです。
実際に展示会でアンケートに回答された経験のある方ならご理解いただけるかと思いますが、項目が多い、記入欄が長いアンケートに回答するのは面倒に感じるものです。
展示会来場者はただでさえ忙しいです。他にもいろんなブースを周るでしょうし、展示会にいられる時間も限られているかもしれません。時間がない中で、できるだけ多くの情報を得たい来場者に対して、煩わしさを感じさせてしまっては、もちろんアンケート回収率は落ちるし、回答してもらえたとしてもその質に関しては疑問が残ります。
つまり、アンケートをされる立場を考えると、その目的を果たすためには、項目設計をよく考えなければなりません。
有効回答数をアップさせる、アンケート設計のポイント
どのようなアンケート設計にするべきでしょうか?
ここで重要なのはいかに来場者の本音を引き出すことができるかということです。
そして、本音を引き出すために確認すべきアンケート設計のポイントは次の3つになります。
POINT1 簡単に来場者の情報を引き出せること
先述した通り、アンケートに回答していただくためには来場者に煩わしさを感じさせてはいけません。限られた時間で多くの来場者に回答してもらうためには、できる限り設問設計をシンプルにする必要があります。
マーケター目線で考えると、得たい情報は山ほどあり、アンケート項目をついつい増やしてしまいたく気持ちもわからなくもないです。しかし、機会損失を少なくするためには、項目はなるべく少なくしましょう。
また具体的な言葉を使い、回答は記入式のものではなく、選択式にしましょう。
POINT2 BANT条件に沿ったアンケート設計
BANT条件という言葉をご存じでしょうか?
BANT条件とはBudget(予算)、Authority(決裁権)、Needs(必要性)、Timeframe(導入時期)の頭文字をとったものです。
シンプルな設問の中でリード(見込み客)の有効度を選別するための指標となるデータを得るために、この考え方は是非アンケート設計に取り入れていただきたいと思います。
| Budget/予算 | 予算はどの程度か? |
|---|---|
| Authority/決済権 | 来場者は決済者か?それとも担当者か? |
| Needs/必要性 | 企業にとって必要性があるか? |
| Timeframe/導入時期 | 導入時期は具体的に決まっているか? |
BANT条件に沿ったアンケートを設計するときには合わせてぜひストーリーを意識してほしいです。営業トークをイメージすればわかりやすいが、いきなり予算について聞かれるよりも、まずはなぜ必要なのかを理解し、その上で詳しい話を進める方が受け入れやすいでしょう。
同様にアンケートにも回答しやすい手順というものが存在します。
BANTに沿ったアンケート項目で言えば、N(必要性)→T(導入時期)→A(決裁権)→B(予算)という設計です。
POINT3 本音を引出すための表現を考慮する
来場者に「予算はいくらですか?」「あなたは決裁者ですか?」と聞いたところで、素直に答えてくれるケースはまずほとんどありません。
そもそも予算や、決裁権などは言いたくないものです。本音を引き出すためには、ちょっとした項目の表現の変化によってBANT条件を盛り込むようにしましょう。
それでは、3つのポイントを抑えた、あるイベントで使用した電子部品メーカーのアンケートを例にして、アンケート設計の見本を見てみましょう。
Q1. 来場者がどのような用途に興味があるのか?
まずは、相手の事を聞く姿勢、まずはオープンザドア効果のある回答のしやすい質問から。
Q2. 出展製品の興味関心はどこにあるのか?
来場者のことを聞いた次は、「うちへの興味は何か?」を聞きたい。
Q3. 現在どのような課題を抱えているのか?
その次は、再度、相手の事を聞く姿勢をつくります。出展製品の次にこの質問を入れることで、その課題をポロッと聞き出しに行きましょう。
以上の3点を聞けば、おおよその具体的なニーズは分かるでしょう。
ここからが、畳み掛けるように来場者の導入時期(T)、権限(A)、予算(B)の条件確認です。
Q4. 導入を検討しているのか?
導入の検討有無に加えて、導入時期を聞きたい。この時期により、イマスグかソノウチ客かを判定していきましょう。
Q5. お客様の職種はなにか?
権限ではなく、職種を聞くことである程度の決済状況を確認することが可能です。これに加えて、役職を確認しても良いでしょう。
Q6. ご導入製品の状況?
つまり、その部品が使われる製品の状況です。新製品開発なのか、基礎研究なのか、置き換えかである程度の予算感は具体的になります。
以上のように、来場者とアンケートを通じて対話をするような設問で、来場者の真のニーズを引き出すことができます。
いま一度、あなたが使っているアンケートを見なおしてみてはいかがでしょうか?
選別できるBANT条件は聞き出しているか、そして、本音を引き出すような設問になっているかを確認してみてください。
営業のモチベーションを上げる、リードの受け渡し方
ここまででアンケート設計のポイントはご理解いただけたかと思います。
アンケート後には結果に基づき、リードを営業へと繋いでいくわけですが、BtoB企業のマーケティング部から、『展示会で集めた名刺やアンケート結果を営業に渡しても、ちゃんと活用してもらえない』ということをよく耳にします。
営業側からすると、ただでさえリードの数が多い上に、商談や受注に繋がるリードが少なすぎるという声が多いです。
確かに獲得したリードが多ければ多いほど、有効度の低いリードに対してはどうしてもアプローチが後回しになるし、結局アプローチさえしないということも考えられます。これではせっかくアンケートに力を入れても結局、機会損失になってしまいます。
ならば、営業が進んでアプローチしたくなるように受け渡すリードを整理してみましょう。もし現状、上記のような状態が社内で見られるのであれば、次に挙げる方法を試してみてください。
その方法はいたってシンプルです。
アンケート結果で有効度が高いと判断したリードのみを営業へ、その他はマーケティング部がWEBやメールマガジンで育成(リードナーチャリング)、継続的に接触を図り機会を伺うという方法です。
この方法であれば、営業の効率もよく、結果として受注率アップにも繋がるでしょう。
どのようにアンケート結果から有効度を導き出すか?については
弊社にご連絡いただければ、御社の業態に合わせた形でご提案させていただくことも可能です。
まとめ
今回の記事でアンケート設計の重要性は感じていただけたでしょうか?
アンケートに求めるべきことは数と質の両方と、2つバランスをとるのは難しいことではあります。しかし、今回取り上げたポイントを抑えたアンケート設計をすることで、今まで以上にブース来場者の真の有効回答数を導き出すことができるでしょう。
一つ一つは小さな改善ではあるが、それらの積み重ねこそがやがて大きな効果を生みます。
是非、次にアンケートを実施する際には、ポイントを抑えたアンケート設計を意識してみてください。きっと効果を実感できるはずです。
Download
Service Plan
ワンマーケティングは、「案件創出」「売上の向上」という成功へ向かって、
ひとつながりのマーケティングフローを構築。
マーケティング戦略設計からMA導入・運用、セールス支援、コンテンツ制作まで統合的に支援しています。
サービスの詳細はこちらから