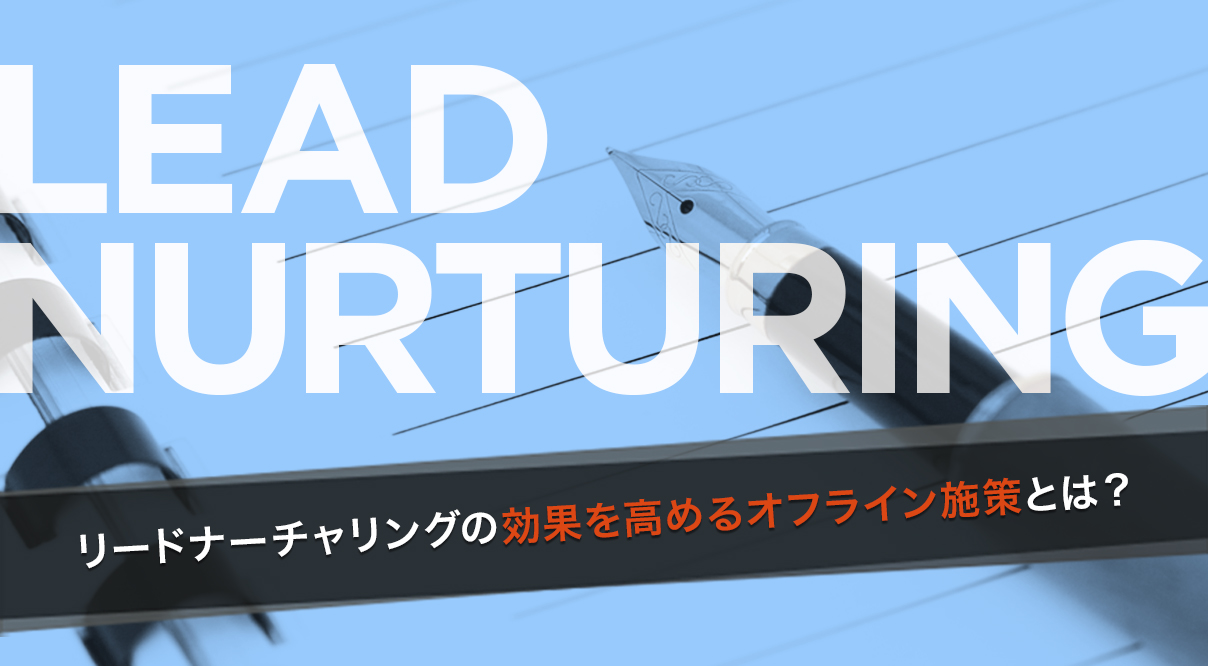顧客育成(リードナーチャリング)とは?基礎知識から優良顧客の育成方法まで解説
目次
顧客を獲得するためには、従来のような飛び込み営業やテレアポではなく、適切な情報発信と顧客育成、つまりリードナーチャリングが大切です。
この記事では、BtoB企業におけるリードナーチャリングについて解説します。リードナーチャリングの意味だけではなく、実施する必要性や背景、具体的な手法なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。
顧客育成(リードナーチャリング)とは
ナーチャリングは直訳すると「育成」となります。ビジネス用語では「顧客育成」の意味で使われます。見込み顧客を購入する状態まで育成する、既存顧客をリピーターとして育成する、どちらの場合もナーチャリングと呼びます。なお、見込み顧客のことを「リード」と呼ぶことから、見込み顧客に対する顧客育成は、リードナーチャリングと呼ぶこともあります。
リードジェネレーションとは?
リードナーチャリングによって顧客の購入意欲を高める前に、まずはリードジェネレーションによるリードを獲得する必要があります。リードジェネレーションとは、自社の製品やサービスに興味を持つリードを見つけ出すことで、この活動がその後の商談や、受注へつながります。
当然ですが、リードが不足していると、リードナーチャリングの対象が減ってしまい、効果も半減します。まずはリードジェネレーションにより、新しいリードを継続的に、獲得することが成功への第一歩です。
リードクオリフィケーションとは?
リードクオリフィケーションは、マーケティング活動における重要な最終プロセスで、「顧客の選別」を意味します。リードナーチャリングによって顧客の購入意欲を高めた後、リードクオリフィケーションにより、購入の可能性が高い「ホットリード」を特定します。ホットリードの選別は、受注確率を高める鍵です。
購入意欲の高いリードを選別するために、スコアリングが用いられることが多いです。顧客の行動や反応、属性に基づきスコアを付け、営業への効果的なトスアップを可能にします。この絞り込みは、リードナーチャリングで育成したリードをさらに精査し、営業の効率を高めるために欠かせません。これらのプロセスを通じ、BtoB企業はより成約率の高い営業活動を展開できます。
既存顧客のリードナーチャリング
マーケティングや営業では新規顧客の開拓に力を入れがちですが、既存顧客を育成することも重要です。既存顧客へナーチャリングを実施することで、アップセルやクロスセルにつなげます。
マーケティングには、既存顧客への販売コストが1なら、新規顧客のコストは5かかるという「1:5の法則」があります。既存顧客の育成は、新規顧客の獲得に比べて手間やコストがかからないため利益率が高くなる、という考え方です。
優良顧客のリードナーチャリング
優良顧客とは、自社への貢献度が高い顧客を指します。一般的には「購入額が大きい」「頻繁に購入してくれる」「最終購入日が近い」、この3点のどれか1点で上位にくる顧客となります。
優良顧客は自社に好意的ですが、より良い商品やサービスを提供する企業があれば、他社へ移行する可能性もあります。これを防ぐために、ナーチャリングによって長期にわたって最適な関係を築くことが大切です。
顧客育成(リードナーチャリング)のメリット
リードナーチャリングのメリットについて解説します。
獲得済みの顧客リストを活用できる
リードナーチャリングでは、企業が保有する休眠顧客情報という貴重な資産を再活用し、新たな商談を生み出すことが可能です。日本の企業が直面するリード獲得の平均費用、すなわちCPL(Cost Per Lead)が8,000円から13,000円という現状の中、コスト効率の高い戦略として注目されています。
出典:第7回 BtoBマーケティングの効果測定と評価 | ITmedia マーケティング
新規リードの獲得には、高額な広告費や展示会への出展が必要となりますが、既に獲得済みである(休眠)顧客リストを活用することができれば、コストを大幅に削減できます。休眠顧客は、過去に企業の製品やサービスに興味を持った経験があるため、新規リードを獲得するよりも成約につながりやすい傾向にあります。このような顧客へのリードナーチャリング施策は、確実性が高く、さらにコストパフォーマンスに優れると言えるでしょう。
また、休眠顧客だけでなく、過去に名刺交換を行っただけ、一度資料をダウンロードしたがそれ以降の行動がなかったなどの既存のリードに対しても、リードナーチャリングは有効です。これらのリードへ積極的にアプローチすることで、再度関心を喚起し、商談機会を増やすことが可能になります。リードナーチャリングは、既存顧客リストの有効活用により、企業のマーケティング効率、コストパフォーマンスを大きく向上させる手法と言えます。
適切な再アプローチを行える
マーケティングオートメーションツール(MAツール)を活用したリードナーチャリングでは、リードの行動や興味を可視化し、ニーズが明確になった瞬間に適切なタイミングでの再アプローチが可能になります。結果として、リードは必要な情報を受動的に収集することができ、同時に企業側の不必要な営業を避けることができます。
これにより、営業担当者は不必要なテレアポや訪問が減少し、業務の効率化を図ることができます。さらに、時間とリソースを無駄にすることなく、高い関心を持つ顧客に集中することが可能になります。
長期的なフォロー体制を構築できる
BtoBの場合、顧客の購入プロセスが長期化する傾向があります。そのため、リードナーチャリングは、長期にわたりリードを効率的にフォローするための重要な手法と位置づけられます。現代のビジネス環境において、WebサイトやSNS、セミナー、展示会など様々な情報収集の手段がうまれました。よって、顧客の意思決定プロセスはますます複雑化し、相当の時間が必要となりました。
リードナーチャリングによって、営業担当者の負荷を軽減し、リードの管理を直感や個人の経験に依存せず、より体系的なアプローチを行うことが可能となります。体系化されたリードナーチャリングを導入することで、企業は顧客との持続可能な関係を築き上げ、その結果として業務の効率性を高め、営業成績を向上させることが期待できます。
顧客育成(リードナーチャリング)のデメリット
リードナーチャリングにはメリットだけでなく、デメリットも存在します。両方を正しく理解した上で、リードナーチャリングを行うことが重要です。
一定数のリストが必要とされる
リードナーチャリングを効率的に行うためには、充分な量の顧客リスト(リード)が必要です。全てのリードの関心度を均一に高めることは実現不可能なので、リード数が少ない限られた顧客リストでは、リードナーチャリングの効果を充分に引き出すことが困難です。一定数以上の顧客リストが必要不可欠なため、前段階であるリードジェネレーションにおけるリード獲得にも注力しましょう。
即時的な効果は見込めない
リードナーチャリングでは、即時的な効果を期待できません。この戦略は、リードの見込み度合いを徐々に高めていく中長期的なアプローチのため、短期間で売上の増加を目指す場合には適していません。効果的なリードナーチャリングを行うには、長期にわたる計画と持続的な取り組みが必要です。
リードナーチャリングは、即効性を求めるのではなく、リードとの関係をじっくりと築いていくことが求められます。長期的な視点から見れば、リードナーチャリングはリードの信頼とロイヤルティを高め、結果として大きな成果をもたらす可能性があります。そのため、リードナーチャリングを成功させるには、短期間での成果ではなく、長期にわたる効果を重視する必要があります。
顧客育成(リードナーチャリング)が重要とされる理由
近年のマーケティングにおいて、なぜリードナーチャリングが重要となったのか、わからない人も多いでしょう。ここでは、リードナーチャリングが重要視される理由について解説します。
顧客自ら情報を収集・比較できる時代になった
インターネットの普及により、顧客は自分から情報を収集できる時代になりました。これにより、従来のプッシュ型のアプローチではなく、顧客に対してWebやメールで有益な情報を発信するアプローチが好まれるようになりました。ベンダーは一方的な押し売りではなく、ナーチャリングを意識した情報発信が必要になっています。
リード獲得経路が多様化した
インターネットの普及により、リード獲得経路が多様化しました。ホワイトペーパーのダウンロードや、製品(サービス)比較サイトからの問い合わせなど、さまざまな方法で潜在顧客が企業に接触するようになっています。しかし、これらのリードの多くは、短期間での成約には結びつかないことが多いです。実際、獲得したリードの約75%が営業活動を行うには不適切な、確度が低いリードであるといわれています。
この背景から、リードナーチャリングが重要視されるようになりました。顧客は購入決定に至るまでにさまざまな段階を経由します。これらの段階ごとに、顧客の状況を理解し、適切な情報提供や関係構築を行うことが重要です。適切なリードナーチャリングを行うことは、リードの質を高め、最終的には販売にも結びつきます。
購買プロセスが厳格化した
Web上の情報量の増加により、購買行動が厳格化しました。特に大企業では、購入プロセスが複雑化し、意思決定に時間がかかるようになりました。これにより、リードナーチャリングの重要性が増しています。
製品やサービスの選定に際しては、社内の稟議・決裁プロセスを経る必要があるので、担当者だけが価値を理解しているだけでは購入には至りません。十分な比較検討や、社内の承認が必要です。このため、リードナーチャリングを通じて、リードの購買意欲を高め、社内での承認をスムーズにすることが重要になっています。
顧客には適切なアプローチが必要になった
選択肢が多様化する現代では、顧客にあわせたアプローチが求められます。そのためには、顧客にとってベストなタイミングでの情報発信や、取引先のニーズに最適化した1on1マーケティングが必要です。リードナーチャリングを実施することで、顧客に対するベストなタイミング、内容でのコミュニケーションを見極められるようになります。
中長期的なマーケティング施策が不可欠
インターネットからの情報取得が容易になったことで、顧客は時間をかけて購入先を比較検討するようになりました。BtoBマーケティングでは担当者に決定権がないケースもあるため、取引のプロセスは中長期化する傾向があります。リードナーチャリングで良好な関係を構築し続けることで、商談や成約に持ち込むチャンスが広がります。
購入意欲を高める取り組みが重要になった
リードナーチャリングは、新規リードの創出だけでなく、購買意欲の低いリードを高確度のリードへと育成する重要なプロセスでもあります。特に、BtoCの高単価商材やBtoBの複数意思決定者が関わる商材の場合、検討期間が長くなりがちです。そのため、リードの取りこぼしは大きな損失につながります。
多くの場合、展示会やWeb広告などで獲得したリードは、自社サービスを知ったばかりで受注確度が低い状態です。リードナーチャリングを通じて、これらのリードを繋ぎ止め、継続的なコミュニケーションを続けることで関係を構築することが重要です。
リードナーチャリングでは、リードの情報収集とニーズの把握を行い、適切なタイミングで関心を高めるコンテンツを提供します。これにより、製品やサービスへの認知を深め、購入意欲の高いリードを継続的に創出することが可能になります。購入意欲を高める取り組みは、現代のマーケティング戦略において不可欠な要素となっており、リードナーチャリングはその重要な役割を担っています。
休眠案件や失注案件の掘り起こしに有効
リードナーチャリングは、一度商談が無効になった顧客にも有効です。見込み顧客として獲得したものの、さまざまな理由から成約まで至らなかったケースもあるでしょう。休眠案件や失注案件を掘り起こすことで、効率的な営業が可能です。1から情報収集する必要がないため、再育成に成功すれば新規顧客を発掘するよりもスムーズに進みます。
顧客育成(リードナーチャリング)に有効な手段・方法
リードナーチャリングにはどのような手段や方法が有効なのでしょうか。ここでは、7つの方法を紹介します。
メールマガジン、ステップメールの配信
メールマガジンやステップメールの配信で、タイトルから社名を覚えてもらったり、開封率・クリック率から顧客の温度感を測ったりできます。メールマガジン配信システムによっては、誰がメールを開封したか、どのリンクをクリックしたかなども把握できます。
顧客の興味関心をひきやすいタイトルや内容、開封されやすい時間帯などを分析し、改善しながらリードナーチャリングを行いましょう。
DM(ダイレクトメール)の送信
DM(ダイレクトメール)は、郵送やFAXを通じて行われる伝統的なリードナーチャリングの手法です。カタログや商品案内を直接送ることで、Eメールよりも高い確率で手に取ってもらえるメリットがあります。
この手法は、特に個人の注意を引きやすく、具体的な情報提供に有効です。しかし、Eメールに比べて、郵送費やFAX代、資料作成費といったコストが高くなるというデメリットがあります。
そのため、より高精度なターゲティングが求められます。DMは、正確にターゲットを絞り込み、パーソナライズされたメッセージを送ることで、その効果を最大限に引き出すことができます。
セミナーの開催
セミナーに足を運ぶということは意欲が高いということです。自社の商品やサービスについてのセミナーを開くことで、確度の高い見込み顧客を獲得できます。顧客のニーズにあわせたセミナーが開催できれば、顧客育成もよりスムーズに進みます。また、顔をあわせて直接話すことで、リードナーチャリングの効果も一層高まるでしょう。
SNSでの発信
SNSは見込み顧客とつながりやすいリードナーチャリングの手法です。SNSは一度フォローしてもらえれば、顧客は受動的に情報を受け取るようになります。また、シェアしてもらうことによって既存顧客だけでなく、新規顧客の目にも触れやすいです。セミナー開催の告知などもできるため、他の手法と組み合わせてリードナーチャリングを進めると効率的です。
ホワイトペーパーの作成
ホワイトペーパーとは、いわゆるカタログのような形式の説明書で、見込み顧客に直接的な効果のある手法です。ホワイトペーパーを企業に向けて発信することにより、競合商品やサービスとの比較がしやすくなります。アプローチした後は、顧客の課題解決のためのノウハウを伝える、具体的な施策を提案するなどしてリードナーチャリングを行います。
Web行動のトラッキング
Web行動のトラッキングとは、自社のWebサイトに閲覧する前に何をみていたのか、どのWebサイトに移動したのかといった、インターネット上の行動の追跡です。これにより、顧客が何に興味を持っているのか把握できます。トラッキングの情報を基にしてメールマガジンの内容を変えるなど、顧客にとって有益な情報を提供するナーチャリングを実施しましょう。
電話でのフォロー架電
フォロー架電はリードナーチャリングにおける重要な手段です。受注や商談の可能性が高いリードに、より直接的なアプローチを行うことで効果を発揮します。
架電は具体的な行動を起こしたリードに焦点を絞って行われます。例えば、メルマガの開封率が高い、セミナーに参加した、問い合わせをした、などの行動を行ったリードが対象です。直接の会話を通じて、リードのニーズを深く理解し、解決策を提案することが可能になります。このような対話は、リードの購入意欲を高めるだけでなく、企業とリードとの関係を強化し、最終的な受注につながる可能性を高めます。
電話でのフォロー架電は、個々のリードに合わせたカスタマイズされた情報提供や、潜在的なニーズの発掘にも役立ちます。
リードナーチャリングを実現するには顧客分析がポイント
効果的なリードナーチャリングを実現するためには、顧客のニーズや顧客情報を深く知ることが重要です。ここでは、効率的に顧客を分析するための有効な手法を2つ紹介します。
購入日や頻度を分類する「RFM分析」
RFM分析は、最終購入日・購入頻度・購入金額を分類する手法です。この3つの要素を基にして、「優良客」「見込み顧客」「新規客」「離反客」の4つのセグメントに分類します。分類したセグメントにあわせたアプローチを行うことで、見込み顧客を新規顧客に、既存顧客を優良顧客にといったリードナーチャリングが可能になります。
顧客の在籍期間を可視化する「CPM分析」
CPM分析は、購入頻度・購入金額・初回購入日から最終購入日までの期間・最終購入日からの経過日数で顧客を分類する手法です。CMP分析では、セグメントを10個に分類します。例えば同じ離反客でも、一度の購入で離反したのか、それとも優良顧客から離反したのかがわかるため詳細な分析や対策が可能です。
リードナーチャリングで成果を出すためのポイント
リードナーチャリングで成果を出すためのポイントを解説します。
適切なKPIを設計する
リードナーチャリングの成功には、適切なKPI(重要業績評価指標)の設計が不可欠です。マーケティング施策の目指すべき成果を具体的に定め、それを実現するために中間指標であるKPIを策定することがポイントです。適切なKPIを設計することにより、リードの購入意欲の変化を効率的に追跡し、施策の優先順位を適切に判断することができます。例えば、メールマーケティングの成果を「受注件数の増加率」とした場合、その中間指標として「フォームへの登録数」や「ホワイトペーパーのダウンロード数」を設けます。
重要なことは、設定したKPIに沿ってPDCAサイクルを実行し、定期的に施策の成果を分析し続け、改善していくことです。
リード情報を統一して管理する
リードナーチャリングの成功には、リード情報の統一、共有、そして管理が極めて重要です。多くの企業ではリード情報が部署やツールを跨いで管理されており、全体像を把握することが困難です。名刺情報のように、個々のメンバーが持つ情報を一つのデータベースや表にまとめ、一元管理する必要があります。
リード数が少ない場合には、スプレッドシートやExcelでの管理が可能かもしれませんが、リード数が増加するにつれて、情報の更新忘れや検索にかかる時間が増え、効率性が低下します。
この問題を解決するために、大規模な事業や十分な予算がある場合には、MAツールを活用することもひとつの手段です。これにより、スムーズなリード情報の更新や、リードの行動履歴の蓄積が可能となり、リードナーチャリングの正確性を向上させることができます。
最も重要なのは、リードに関する詳細情報をチーム全員で共有し、効果的なリードナーチャリング戦略を策定することです。これにより、各リードに最適なアプローチを特定し、リードの品質を向上させることができます。
スコアリングによりホットリードを特定する
リードナーチャリングの成果を最大化するためには、スコアリングを通じてホットリードを特定することが重要です。スコアリングでは、リードの行動にスコアを割り当て、その合計値でリードの興味や購入意欲の度合いを数値化します。具体的には、メールの開封、メール内のURLクリック、ホワイトペーパーのダウンロードなどの行動に基づきスコアを付与します。さらに、リードの属性情報(業種、役職、部門など)にもスコアを設定し、行動スコアと組み合わせることで、スコアリングの精度は一層高まります。
スコアリングを設定することで、高得点を獲得したリードをホットリードとして識別することができます。ホットリードとは、自社の製品やサービスに対して高い関心を示しているリードのことを指します。ホットリードに対して適切なアプローチを行うことで、効率的なリードナーチャリングが実現します。ホットリードの定義を明確に設定することで、リードの質を正確に評価し、営業活動における優先順位付けやリソースの最適な配分が可能になるのです。
定義が不明確では、見込み度合いに適さない施策を行ったり、営業機会の損失につながったりするため、ホットリードの定義を明確にしてスコアリングの適切な設計と運用が重要です。スコアリングを活用することで、リードの状態を客観的に把握することができます。結果として、営業チームへの引き渡しをより精確に行うことができ、リードナーチャリングの成果を大きく向上させることが期待できます。
MAツールを導入する
リードナーチャリングの効率化にはMAツールの導入が有効です。MAツールにより、リードナーチャリングの自動化を実現できます。
MAツールは、リードの行動や状態に応じたシナリオ設計と自動ナーチャリングの設定が可能となり、人的リソースの削減に役立ちます。例えば、セミナー参加後のフォローメール送信や、特定のWebページ訪問者へのコンテンツ提供などが可能です。MAツールは製品により機能、コストが大きく異なります。ツールを選択する際には、自社に必要とされる機能を見極め、予算と費用対効果を考慮して、慎重に比較検討を行いましょう。ビジネスのニーズに合致するツールを選ぶことが大切です。
営業とマーケティングチームが密に連携する
リードナーチャリングで成果を出すためには、営業とマーケティングチーム間の密接な連携が欠かせません。受注や商談への成果を最終目標として、マーケティングチームがリードナーチャリングを行い、営業チームが購入意欲の高まったリードであるホットリードを受け取ります。インサイドセールスチームはこの橋渡し役として、マーケティングから営業へのリードのスムーズなトランジションをサポートします。
リードの引き渡しにおいて、獲得経路やアプローチ履歴などの詳細情報を共有し、チーム間で連携して進めることが必要です。マーケティングチームはリードナーチャリングを担当し、営業チームは育成されたリードを受け取り、商談へとつなげる責任を負います。両部門間の情報共有と連携を深めるためには、マーケティングオートメーション(MA)やセールスフォースオートメーション(SFA)などのITツールの活用が推奨されます。これにより、各リードに対する適切なアプローチと追跡が可能となり、成約率を高めることができます。
顧客情報の管理・分析を効率化させるツール
より良いナーチャリングには、顧客情報の管理や分析を効率化させることが重要です。ここでは、顧客情報の管理・分析を効率化させるツールを2つ紹介します。
CRMツール
CRMツールは顧客管理システムです。CRMツールでは顧客の担当者の氏名や部署名、連絡先などの基本的な情報から商談履歴、アプローチ結果などを管理できます。さらに、蓄積した情報を分析できることも特徴です。収集した情報を組織全体で共有できるため、顧客にあった適切なアプローチやフォローがしやすくなります。
MAツール
MAツールはマーケティング活動の一部を自動化するためのツールです。メール送信などルーティン業務の自動化だけでなく、見込み顧客の情報やWebサイトの閲覧履歴などを基にして、見込み度合いのスコアリングもできます。見込み度合いにあわせて適切なタイミングで有益な情報を自動で発信できるため、ナーチャリングに役立ちます。
リードナーチャリングを始める実践ステップ
これまでの解説のまとめとして、リードナーチャリングを始めるための実践ステップを解説します。
ターゲットの整理と理解
リードナーチャリングを始める際の最初のステップは、対象となるターゲット群を特定し、その特性やニーズを深く把握することが必要です。ターゲットはさまざまな業種、職種、役職にわたるため、具体的に誰をリードナーチャリングの対象とするかを明らかにすることが重要です。
次に、ペルソナ設計と購買プロセスの理解に移ります。ペルソナ設計を通じて、ターゲットの特徴、関心事、課題を具体化することで、それぞれのニーズに合わせた情報提供が可能になります。例えば、マーケティング部門のリードであっても、役職によって求める情報は大きく異なります。これを踏まえ、コミュニケーションの内容や手法をカスタマイズする必要があります。
顧客の購買プロセスを理解することで、それぞれのリードがどの段階にいるのか、どのような情報が役立つのか判断することができます。このプロセスを把握するためには、ASICAなどフレームワークの活用や営業担当者との密なヒアリングが有効です。ASICAのフレームワークでは、課題(Assignment)、解決(Solution)、検証(Inspection)、承認(Consent)、行動(Action)の流れに沿ってモデル化して考えます。
ターゲットが日常的に行っている業務内容、抱えている課題、購買に至るまでのプロセスを理解することが、リードナーチャリングの効果を最大化します。ターゲットの整理と深い理解を基にしたリードナーチャリングは、より効果的なコミュニケーションを実現させるための鍵となります。
リードの現在のステータス把握
続いて、リードの現在のステータスを正確に把握します。リードのステータスを理解することにより、各リードに合わせた適切な情報提供やコミュニケーション手法の選定が可能となります。リードの状態には、連絡未達のリード、まだ架電を試みていないリード、営業と積極的にコミュニケーションを取っているリードなど、さまざまなタイプが存在します。
これらのリードの状態に応じた適切な方法でアプローチすることが、効果的なリードナーチャリング戦略には欠かせません。
セグメントの作成
次の段階となるセグメントの作成は、リードナーチャリングの実施において必要不可欠です。顧客の業界、職種、役職などの基本属性や、過去の取引履歴、獲得経路をもとに細かく顧客を分類し、顧客セグメントを作成します。これにより、製品やサービスへの関心が特に高い顧客グループを特定できます。
セグメントの作成には、データ管理と分析を容易にするMAツールの利用が推奨されます。しかし注意点もあります。セグメントを過度に細分化すると管理が複雑になるため、実務上の効率性とバランスを考慮することが大切です。商材や業界によっても適切なセグメント数は異なりますが、一般的には、10種類程度のセグメントを作成することが理想的です。適切なセグメント化により、各リードに対してパーソナライズされたリードナーチャリング活動を行うことが可能となり、リードの関心を高め、最終的な成約率の向上に貢献します。
コンテンツの整理・作成
リードナーチャリングの成功には、ターゲットに合わせたコンテンツの整理と作成が不可欠です。最初に、セグメント化された顧客群の特徴を分析し、それぞれの購買プロセスに応じた最適なコンテンツを提供することが重要になります。例えば、展示会で名刺交換をしたリードは、見込み度合いが低いため製品の基本情報を提供するノウハウコンテンツや無料セミナーの案内などが有効です。これに対し、自社Webサイトで資料請求を行ったリードには、興味関心が高まっていると判断できるため、導入事例や特別キャンペーンの情報が適切です。
次に、既存のコンテンツを活用できないか検討します。既に作成されているコンテンツが活用できるのであれば、新規作成の手間とコストを削減できます。しかし、組織内で情報共有が不十分な場合、既存コンテンツを見過ごし、不必要に新たなコンテンツを作成してしまうこともあります。
既存コンテンツを十分に活用した上で、足りない部分について新規のコンテンツ作成を行います。リードの見込み度合いに応じて、ノウハウ系のコンテンツから製品やサービスの詳細説明に至るまで、多様なコンテンツを用意することが、リードナーチャリング効果を高める鍵です。この段階的かつ目的に応じたコンテンツ提供により、リードを効率的に育成し、最終的な成約に繋げることが可能となります。
施策の実施
最終段階では、セグメント化した顧客ごとに最適化されたコンテンツを配信し、その反応を細かく分析することが必要です。顧客の行動、例えばメール開封率やWebサイト訪問数などを測定し、これらのデータをもとにコンテンツの調整や改善を行います。
効果的なリードナーチャリングを実現するためには、施策の効果を定期的に検証し、フィードバックを反映させることが欠かせません。PDCAサイクルを迅速に回し、顧客ニーズに合った情報を継続して提供することで、リードの購入意欲を高めることができます。このプロセスを通じて、リードナーチャリングの成果を最大化し、顧客との関係を深めていくことが大切です。
リードナーチャリングの実践事例
リードナーチャリングの実践事例を解説します。自社の状況に置き換えて、取り入れられることがないかを考えながらご覧ください。
実践事例1:フォロー体制の構築
BtoB向けのWebサービスを提供するA社では、Webサイトや広告を通じて獲得したリードに対して、インサイドセールスが架電を行い、セミナーへの参加を促しています。
しかし、リードの中には「タイミングが合わない」や「現時点の具体的なニーズがない」と反応するケースも見られます。その際、A社はリードを放置せず、最初の断りを受けてからも適切な時期に再度アプローチを試みる仕組みを構築しています。この継続的なフォローアップ戦略により、断られたリードとの長期的な関係を築き、より多くの商談を生み出す可能性を高める取り組みを実践しています。
実践事例2:失注リードの有効活用
不動産事業を手がけるB社では、MAツールを駆使してリードナーチャリングの仕組みを構築しました。このシステムを通じて、特定のターゲットへメールを送信し、メール内のリンクをクリックしたリードには、インサイドセールスが即座に架電を行います。
特に、過去にアポイントを断わられたり、商談化したが成約には至らなかったリード(=失注リード)を再活用する戦略を行い、月間約50件のSAL(Sales Accepted Lead:営業受け入れリード)の創出に成功しました。この取り組みは、一見見込みの薄いリードからも新たな営業機会を創出できるリードナーチャリングの可能性を浮き彫りにしています。
顧客の育成や関係維持には1to1マーケティングで最適化を
顧客の育成や良好な関係を維持するためには、1to1マーケティングが重要です。最適なタイミングで顧客にとって必要な情報を提供することが求められるため、パーソナライズは欠かせません。
さまざまな情報や商品・サービスが溢れている現代では、大多数へのマスマーケティングは効果が薄くなりました。そのため、1企業ごとにカスタマイズした情報発信や商談の提案が必要です。カスタマイズした有益な情報や提案による、良好な関係の維持が、ナーチャリングの成功につながります。
まとめ
顧客自身が情報を取捨選択できる現代において、競合他社に先んじて選ばれ続けるためには、ナーチャリングの実施が重要です。ナーチャリングをスムーズに行い、BtoBマーケティングを軌道に乗せましょう。
ワンマーケティングではMA導入支援やコンサルティングを行っています。MA運用に必要なMA設定やコンテンツ制作まで併走支援できるのは、ワンマーケティングだけです。ノウハウが詰まった資料を配布しているため、ぜひダウンロードしお役立てください。
マーケティング支援について
ワンマーケティングは、「案件創出」「売上の向上」という成功へ向かって、ひとつながりのマーケティングフローを構築。マーケティング戦略設計からMA導入・運用、セールス支援、コンテンツ制作まで統合的に支援しています。
Download
Service Plan
ワンマーケティングは、「案件創出」「売上の向上」という成功へ向かって、
ひとつながりのマーケティングフローを構築。
マーケティング戦略設計からMA導入・運用、セールス支援、コンテンツ制作まで統合的に支援しています。
サービスの詳細はこちらから