
展示会の成果はフォローで決まる
展示会の来場目的の94%は情報収集であるという事実
展示会の来場者数が年々減少傾向にある中、インターネットを中心とした情報収集の選択肢も多様化しています。
さらに展示会の来場目的の94%が情報収集である一方、出展企業は多くの商談を獲得したいという思惑が、ある展示会の来場者アンケートの結果でも明らかになっています。
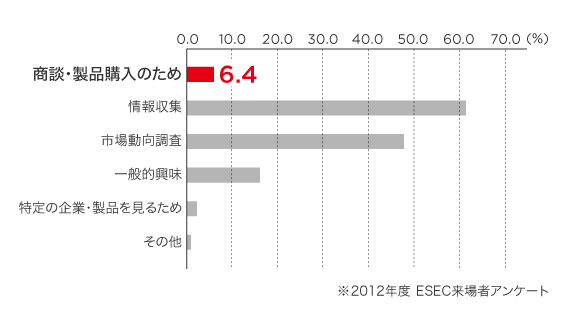
そのような中で展示会から商談があったとしても、偶然見込み客の購入タイミングが展示会に重なった可能性が高いということを出展する企業は認識しておく必要があります。
大きな需要だけを求めて展示会に出展するのは、止めなければなりません。
フォローはマーケティング部門が実行する
BtoBマーケティングラボの様々な記事でも紹介していますが、BtoBの購買プロセスは長期化する傾向にあり、いますぐの売上を優先したい営業マンだけでは、長期に渡り見込み客との接点を維持し、顧客化することが難しくなっています。
「来場目的の多くが情報収集であること」、「購買プロセスがより長期化していること」を踏まえた上で展示会の役割を考えてみると、会期中の商談ではなく、見込み客を獲得するための手段として力を入れるべきです。
また、獲得した見込み客リストはそのまま営業に渡すのではなく、購買のタイミングがやってくるまでマーケティングチーム側でナーチャリング施策を実施しましょう。
事前にしておくべきフォローのための準備
案外、展示会を実施することが目的になってしまっている企業は多いです。そのため、フォロー施策に対して考えが希薄であり、予算すら付いていない企業もあります。
展示会を見込み客獲得の機会と捉えるのであれば、展示会は始まりと考え、ぜひ二の矢、三の矢を射っていきたいところです。
会期後にフォローの準備をするのではなく、アンケートの回答に対して、どのような行動をおこすべきか、すべてを営業に任せるのではなく、営業ではまだ早すぎる見込み客に対してどうフォローすべきかを事前に検討しておくことが必要です。
準備1:営業のリソース状況は?
まず考えるべきは、展示会後にすぐ商談に繋がりそうな見込み客に対して、即動ける営業人員のリソースはどれくらい確保できるかです。
考え方の例としては、
①営業マン1人あたりの1日のフォロー可能件数を割り出し、
②その件数と展示会後1ヶ月にかけられる人員を掛けた数
が展示会後に営業へ送客可能な件数となります。
例えば、
①1人あたりの1日のフォロー可能件数が2件ならば1ヶ月の件数は40件。
②その人員が5人いるならば200件のリード(見込み客)
を営業へ送客することは可能です。
1つの展示会で2,500件のリード獲得があったとすれば、アンケート結果などから優先順位を付け(※優先順位のつけ方は後述)、見込み度の高い上位200件を送客すれば良いわけです。
あとの残り2,300件はマーケティング部門のナーチャリング対象となります。
準備2:データのフォーマット化
展示会で獲得した名刺やアンケートは会期後にデータ化しましょう。
しかしそのデータフォーマットが展示会ごとに違うことはありませんか?
その場合、顧客データの持ち方自体を考え直しましょう。たとえば既に主体として使っているCRMがあれば、そのフォーマットに合わせてデータ入力をする必要があります。
もし無ければ共通のフォーマットを作りましょう。
そして展示会毎に発生する個別のアンケートなどは、このフォーマットの中に入れるかどうかも検討しましょう。入れる入れないかの基準は、『そのデータは1年後に役に立つ情報か?』です。
大抵は必要のない項目が多いので、精査に精査を重ねましょう。
準備3:スコアリングによる優先順位の決定
アンケート、ヒアリングシートを作成する上で盛り込むべきはBANT条件です。
以前に「真の有効回答を導き出す方法! 展示会のアンケート設計における重要な3つのポイント」に関する記事を書いたので、詳しくはそちらをご覧ください。
簡単に概要を説明すると、
BANTのBはBUDGET(予算)、AはAUTHORITY(決裁)、NはNEEDS(関心・必要性)、TはTIME FRAME(時期)。これらの設問をアンケートに盛り込むと良いでしょう。
ただし上記条件は、時間とともに変化する情報です。したがって、現時点において営業に送客すべきかの判断軸となります。
優先順位は各設問に対してスコアを付け決定します。マーケティングオートメーションを既に導入しているならば、これらのスコアはデータをインポートした時点で管理できるので非常に便利です。
※スコアリング例
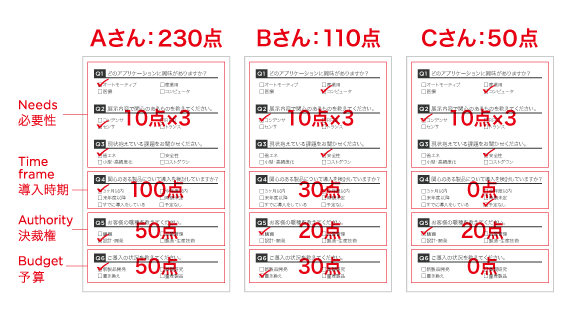
準備4:情報収集手段の確認
展示会で獲得できる情報収集手段の確認も事前にしておきましょう。
アンケートや名刺データは、自社で準備、回収するため、先述したフォーマットの命名規則に沿ってデータ整理が可能です。
しかしバーコードデータの取り扱いが難しいケースが多いです。バーコードデータは、主催者のホームページから来場登録を実施するため、かなりデータの中身が荒れます。
また、項目の持ち方も出展主催者によりマチマチになるため、展示会後のクレンジング作業が必須です。アンケートの項目が揃わない場合もよくあるので、その場合は、各項目のマッピングをし直す必要がある。予め対応策を検討しておきましょう。
準備5:展示会後のフォロー策の検討
展示会後、営業はどのようにフォローするか、マーケティングからはどのように接点を持ちリードナーチャリングを実施していくか検討しておく必要があります。
その際に、スコアリングの数値やアンケートの回答内容を基準とします。
見込み度のランクをイマスグ、ソノウチ、イツカハに分け、
イマスグの見込み客は営業へ、ソノウチはテレマーケティング、イツカハはナーチャリングというように分担していくのも一つの手段です。
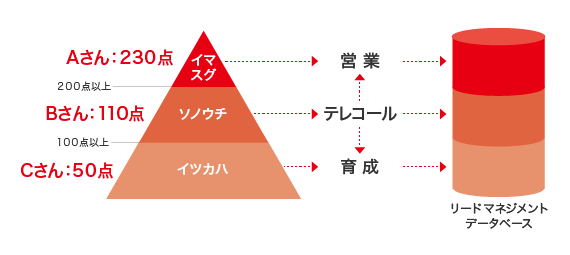
テレマーケティングも人的コストがかかるので、予算、リソースを考慮し、どこまで実施するかを決めたうえで検討しましょう。
準備6:アフターフォローのコンテンツ検討
展示会後にサンキューメールを送る企業は多いですが、それだけでは全く効果がありません。
それに見込み客は、一斉配信で送られてきた『来てくれてありがとう』という内容のメールを求めてもいないことは想像に容易いと思います。
展示会に関連するセミナーやホワイトペーパー、パネルのダウンロードなど、次のアクションを促すためにも、見込み客にとって価値のある何らかの情報提供を望まれているし、実施することが重要です。
特にマーケティングオートメーションを導入済みの企業にとって、送ったメールコンテンツをクリックしてもらうことは、獲得した見込み客情報と行動の紐付けを行う重要な機会の1つです。
マーケティングオートメーションでのWebトラッキング(Web上での行動情報を収集)は、配信されたメールのコンテンツに対するクリックがキーとなり開始され、その時点で見込み客情報と紐づけされます。その後の見込み客とのタッチポイントや行動を管理するという観点からも、サンキューメールの内容、その後のフォローのコンテンツは非常に重要です。
また、まだマーケティングオートメーションの導入がなされていないという場合でも、せめてメールをクリックしたユーザーが誰であるかはわかる配信ツールを選んでおきたいところ。ただあくまでもメールのクリック、そこからの流入は受け身の行動であり、見込み客の確度の高まりを示すのは、そのあとの能動的な行動にあります。そのポイントを把握するためにもマーケティングオートメーションは導入しておきたいところです。
展示会のタイミングは見込み客のタイミングではない
見込み客のタイミングを掴むためには、やはり中長期に継続的な接点を作り続けることが求められる。展示会の効果は長い期間を経て、初めて効果が出るものです。
イマスグの短期的な需要を掘り起こすためには、展示会におけるリード獲得の母集団を大きくすれば良いですが、そこだけにフォーカスしても何も変わりません。『圧倒的に数が多いのはイマスグではない、ソノウチ、イツカハに該当する見込み客であること』を意識することです。
そして、これらの客をに対して適切な対応をしていくのは、営業ではなくマーケティング担当者です。
展示会のデザイン、企画に時間、コストを費やすのはともかく、フォローありきのプランニングを今一度考えてみましょう。
Download
Service Plan
ワンマーケティングは、「案件創出」「売上の向上」という成功へ向かって、
ひとつながりのマーケティングフローを構築。
マーケティング戦略設計からMA導入・運用、セールス支援、コンテンツ制作まで統合的に支援しています。
サービスの詳細はこちらから




